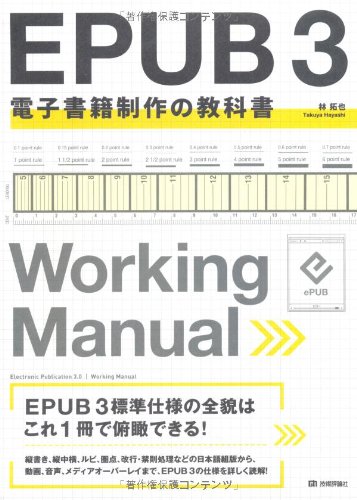読書端末の快感
最近、ソニーReaderで漱石wを読んでいますが、実にスムーズに読めて、あらためて電子ペーパー式の読書端末の有用さを実感しています。
実際の読書スピードはどうだか分りませんが、感覚として何の抵抗もなく流れるように読み進めていける感じ。読書端末を使い始めてから、これまで何の疎ましさも感じなかった紙の本に、ある種、読書そのものを妨げる物理的な要素があったのだということに、初めて気づかされたという気がしています。
「何の疎ましさも感じなかった」と書きましたが、ちょっと訂正。最近、本を手に取るごとに、かすかな負担感のようなものを無意識のうちに感じていたのはまぎれもない事実のような気がします。重たさがいけないのか、表紙の固さや角のとんがりがいけないのか、はたまたあまり読書の興にプラスになっているようにも思えないハデなカバーデザインが鬱陶しいからなのか、読書という行為に行き着くには、越えなければならない小さなハードルが確かに存在するのです。
まあ年のせい、と断言してしまっていいのでしょう。若い頃の烈々たる読書欲が衰えて、それと入れ代わりに、若い頃は意識さえしなかった読書の肉体作業的側面が前に出てきた。もちろん肉体的に一番負担を受けるのは脳味噌でしょうが、それを忌避すれば読書自体が成り立ちませんから、問題はそれ以外の外的な負担、すなわち紙の本の物理的性質から起因するものということになります。
あ、そうそう、視力のこともあります。衰えた目にはもちろん小さな活字は大敵ですが、それだけでなく本ごとに活字が違う、フォントの種類やサイズ、字送り・行送りがバラバラなのも、考えてみたら衰えた目にはそれに慣れるまでに少々時間を要する、一種の負担なのではないかという気が(重箱の隅を突つくようですが)しています。そして、この活字の問題も紙の本の物理的性質の一つです。
では、読書端末にはそうした物理的ハードルがないのかというと、もちろんあります。でも、それらは一定なのです。いつも同じ箱体の同じ手触り。活字もデフォルトのサイズが選べて、フォントも一定。ページ送りもボタン式にしてもフリック式にしてもいつも同じで、紙の本のように、紙の厚薄、本の大小、綴じ方や背表紙の固さによって、手が受ける感触、持ち扱いの作法が千変万化するということがない。そして、一定であることによって、それらは無意識化・抽象化され、物理的な負担感はどんどんゼロに近づく、といえば大仰かもしれませんが、それに近い感触を自分などは感じています。
つまり、読書端末を通して、人は著者の草した素の文章によりダイレクトに接することができる。そこでは紙の本の物理的性質からくるさまざまな夾雑的感覚を忘れて、ニュートラルに文章世界そのものを楽しむことができるのです。
いやいや、読書というのは、本の装幀やページの姿、紙の手触りやインクの匂い、つまり視覚・触覚・嗅覚と一体となって楽しむものであって、そんな素の文章が幻影のように宙に浮いているだけなんて、頼りなくて、味も素っ気もなくて耐えられない。そんな反論もごもっともだと思いつつも、今の私は、紙と電子、両方が選べる場合は、上のような理由から、たいてい迷いなく後者を選んでしまうと思います。
ただし、ごく愛着の深い、何度も読み返したい、いつも近くに置いておきたい著者の場合は、紙の本を選ぶだろうと思います。電子本にはまだそんな偏愛を受けとめられるだけのクォリティが不足しているからです。この先、そんな質を獲得できるかも不明です。実は、このサイトで公開している鏡花の短編選は、自分なりに愛着の持てる電子本をめざして試作してみたものですが、これも紙面固定的なPDFというフォーマットとソニーReaderというステージを前提としているからこそできること。これから主流になるだろうepubなどのより流動的なフォーマットで、かつ機種横断的にそれができるかは、今後の日本の本読みの電子書籍への肩入れ次第かなという気がしています。