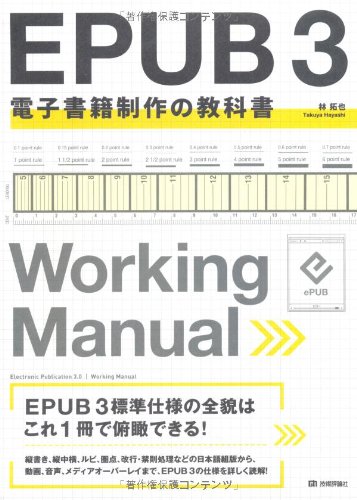『花月新誌文集』制作余話
先月出版した『花月新誌文集』は4冊目の柳北本です。最初はここまで成島柳北にこだわることになるとは思っていなかったのですが、知れば知るほど幕末・明治前期の文筆家としては抜群の存在であることが分かり、それに比して認知・評価が低いことが残念で(さすがに加藤周一の文学史にはかなりのスペースが割かれていますが)、そのギャップを埋めるべく微力を投じてみた次第です。
とはいえ、素人の中途半端なアプローチではかえって柳北先生の真価を傷つけるのではないか、という心配もなきにしもあらず。確かに注釈面では、たとえば岩波文庫で今唯一読める柳北本『航西日乗』の綿密な注に比べれば、その至らざること甚だしいものがあります。ただ本文に関しては、あの句読点や段落もなく、ルビも最小限の片かな交じり文という原典を、なんとか読めるものに仕上げることができているのではないかという自負もあります。
柳北本はこれにて打ち止め、と言いたい所ですが、実はまだ超大物が控えています。それは朝野新聞に10年間に渡って執筆した「雑録」で、これこそは明治以後の柳北の代表的な仕事といえるものです。ただ、その数は膨大で、しかもその数を確定することさえ難しいという難物です。というのも、朝野新聞に掲載した際に柳北の署名があるものはごくわずかだから。しかしその他の多くも柳北の手になるのではないかと思わせる証拠は多々あります。つまり「朝野新聞雑録集」の出版を志す人は、まず膨大な「雑録」一つ一つを吟味して柳北の筆触を見分けるという作業から始めなければならないのです。
もしそれができたと仮定しても、その後は例の原典との格闘が延々と続くわけで、これはどう考えても一個人出版者の手に負えるものではないでしょう。とはいえ、これにせめて目を通しておかないと柳北を理解したとはいえないのも事実。元気のある時に、図書館にこもって朝野新聞縮刷版から柳北コラムを抽出する作業をやってみたいと考えています。本にするかどうかは、その先の問題。
さて、「余話」といいつつさらに前置きが長くなってしまいましたが、今回の『花月新誌文集』ではこれまでの柳北本と作り方を変えたことが一つ。これまでは注をまとめて巻末に置いていたのを、今回は一編ごとに置くようにしました。というのも、本文からリンクで注記に飛び、また戻るという端末・アプリ上の操作がうまくいかない場合も少なくないのではないかと考えたからです。最悪の場合読み手は巻末に取り残されて、読んでいたページまで手探りで戻るという迷惑至極なことになります。その点、一編ごとの注では手作業で戻っても数ページで、許容範囲でしょう。また制作面でも、注に番号を振る場合、全巻通し番号の注では、追加や削除が出た時の番号の振り直しが面倒なのが回避できます。以後、できるだけ小さな単位で注をまとめるという原則でやっていきたいと考えています。
ところで、毎回頭を悩ませるのが表紙のデザイン。内容と関係があって、絵的にも面白そうなものをと考えるのですが、もちろんプロが作るようにはいきません。ただ、最近の電子書籍の表紙の傾向として、親しみやすさを考えたためでしょうが、やたらと漫画チックなものが多いのは、ちょっとどうかと思います。吉川英治までが劇画調の表紙になってたのにはあきれました。まあ、電子書店はどうしてもカタログ的な表紙の一覧というスタイルになりますから、目を引いてスクロールの手を止めさせるという点で、表紙のインパクトは印刷本以上に重要です。そして、今のところ主な客層である若者は多くが漫画から電子書籍に入っているでしょうから、小説などの表紙も同じ雰囲気でということになるのかもしれません。しかし、本来、物語本の最大の強みは文章を通して読者の想像力を刺激し、自由にイメージを羽ばたかせることができる点。なのに表紙に登場人物などの具体的な絵を載せてしまうというのは、出版社自らがその機能を狭めたと言われても仕方のない悪手だと思います。たぶん著者にとっても迷惑千万でしょう。
それはともかく、『花月新誌文集』の表紙はタイトルバックに小林清親の版画を使いました。この絵には花盛りの隅田堤と川遊びが描かれていて、この本で柳北が繰り返し讃えてやまない墨堤爛漫の楽しみにぴったりだったからです。実はこの絵に行き着くまでには、高橋由一の「墨堤桜花」でどうかと画集を買ってみたり、古い桜の名所の写真を探したり、結構右往左往しました。しかし、そんなことが個人出版の楽しみの一つだったりもします。小林清親の版画を見つけたのは「Ukiyo-e.org」というサイトのおかげですが、これがまたすばらしいデータベースで、蛇足ながら浮世絵に興味のある方にはお勧めです。